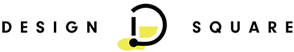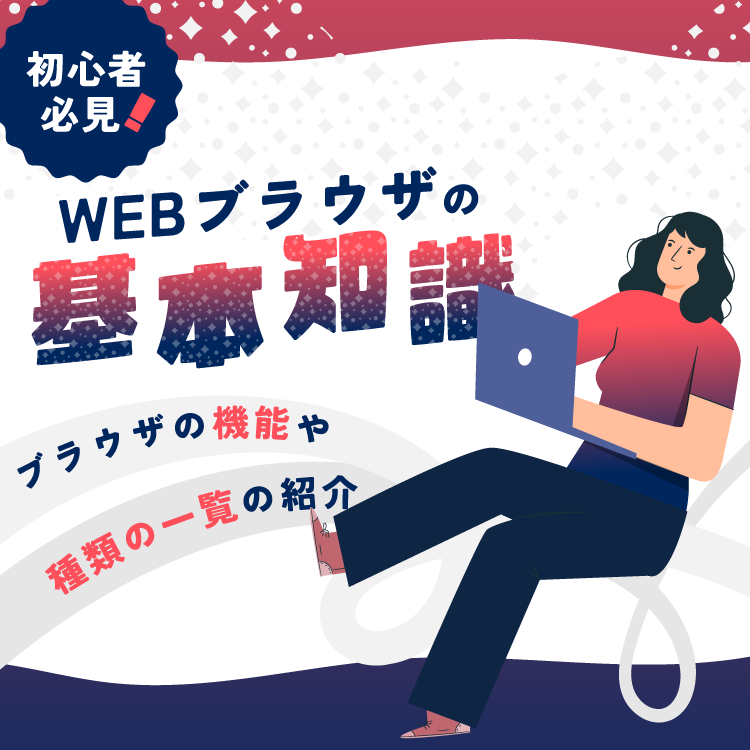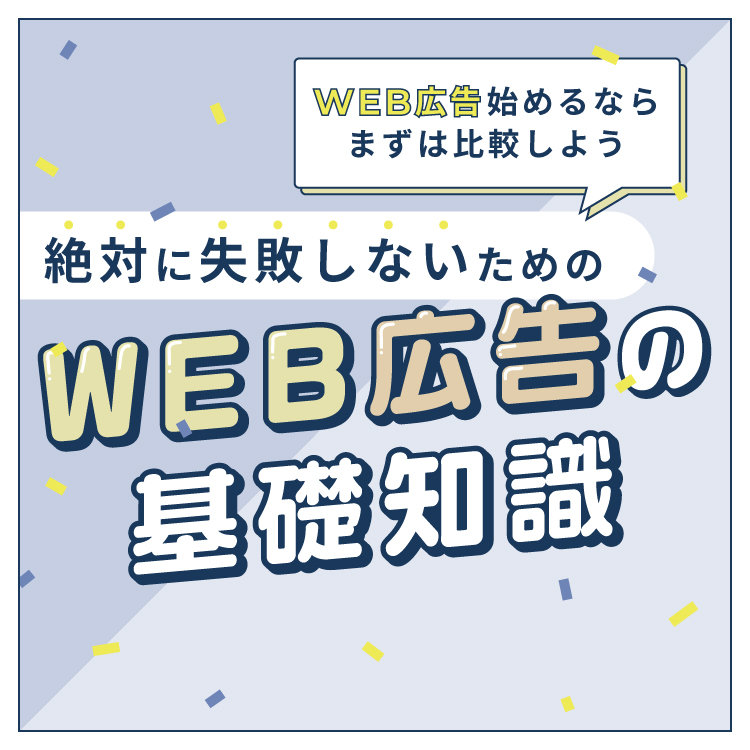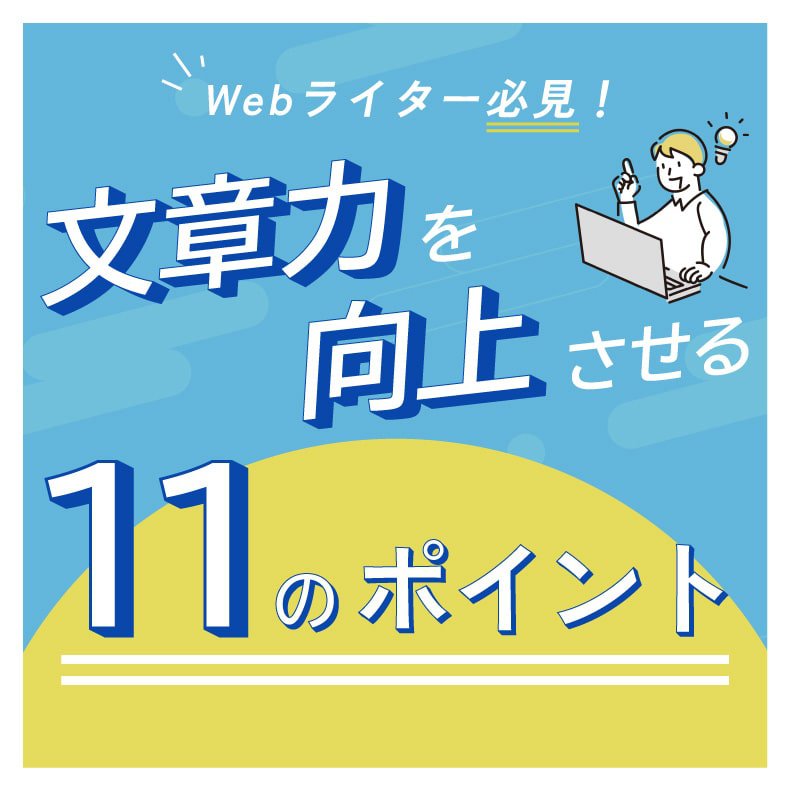あなたは、WEBライターとしてどのようなことに気を付けていますか?
Webライターには、知っておかないとトラブルに発展してしまうようなNG行為がいくつか存在します。
今回は、それらのWEBライターがやってはいけない行為を解説します。
他サイトの記事をコピーする
WEBライティングにおいて、絶対にやってはいけない行動の一つが「コピー&ペースト(コピペ)」です。
他人の著作物を無断で使用することは法律違反であり、訴訟や損害賠償請に発展することもあります。
こうしたトラブルは、ライターにとって致命的なダメージを与えるだけでなく、クライアントにも迷惑をかけてしまうため、絶対に避けなければなりません。
またGoogleは、コピペで作成した記事を独自性のないコピーサイトとして認識し評価を下げます。
そのためSEOの観点でも大きなマイナスとなり、検索結果の順位が上がらなくなってしまうため、コピペや盗作をしないという基本ルールを守りつつ、引用やリサーチを活用した正確かつ独自性のある記事を書くことを心がけましょう。
コピペチェックでトラブル回避
コピペと判断される文章は、一字一句同じものだけではありません。
語尾や語順を変えただけの文章も、コピーサイトと判断されてしまいます。
そのため、意図的でなくても、すでにネット上にある記事と同じ情報に関する記事で、表現や言い回しが偶然似てしまい、コピーサイトとなってしまう場合があります。
以下のようなコピペチェックツールを利用して、他サイトのコピペになっていないかアップロードする前に確認しましょう。
無料
有料
引用元を記載しない
他サイトの文章や画像などを引用する際は、必ず引用元を記載しましょう。
出典を明記していなければコピペと同じになり、法律違反となってしまいトラブルに発展する可能性があります。
また、情報の信頼性を担保するといった点でも重要な要素になっています。
引用から引用する「孫引き」にも注意が必要です。情報を引用する際は、原典を確認しましょう。
引用をする際に確認するポイントは次の通りです。
- 引用元の転載が禁止されていない
- 引用が不可欠である
- 自分で執筆した部分がメインコンテンツである
- 引用したものを加工しない
- 引用部分を明確にする
引用と出典の記載方法
引用部分を明確にするために、次のような方法で本文と差をつけましょう。
1.引用部分を引用符や括弧で囲む

2.背景の色を変える
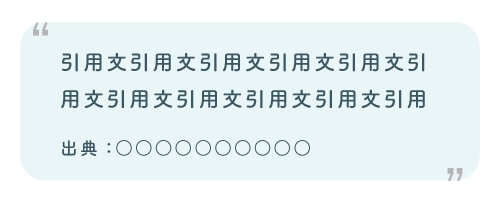
3.書体を変える
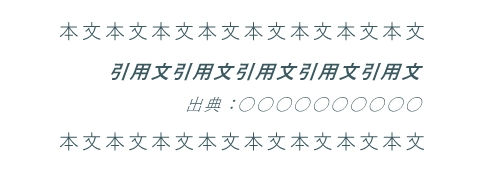
出典は、リンクがある場合はサイト名とリンクを設置し、書籍の場合は著者名、書名、出版社、出版年、ページをそれぞれ記載しましょう。
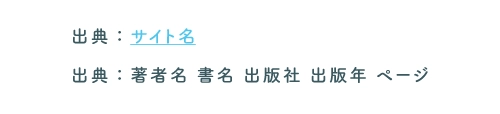
引用箇所に使うHTMLタグ
HTMLにも、引用する際に使う引用タグがあります。
blockquoteタグ
タグ内のテキストが引用文であることを示すものです。引用する文章が長文である際に用いられます。
例
<blockquote>
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○
</blockquote>
qタグ
タグ内のテキストが引用文であることを示すものですが、blockquoteタグとは違い引用する文章が短い場合に用いられます。
例
<q>○○○○○○○○○○</q>
citeタグ
引用元を明記する際に用いられます。
例
<cite>○○○○○○○○○○</cite>
曖昧な情報を記載する
曖昧な情報は、記事全体の信頼性を損なう原因となります。
特にSEOにおいては、正確で根拠のある情報の提供が求められ、これに反する内容は検索順位にも悪影響を与える可能性があります。
例えば、「多くの人がこう言っています」や「一部で話題になっています」といった曖昧な記載では、読者が情報を裏付ける根拠を得られません。
曖昧な情報を避けるためには、信頼性の高いデータや資料を元にリサーチを徹底することが重要です。正しいリサーチを怠ることで事実と異なる情報を掲載する危険性もあります。
誤った情報を拡散してしまうと、読者からのクレームやトラブルに発展するリスクもあるため注意しましょう。
略称の使用
略称を使うことも、WEBライティングでは避けたほうが良いでしょう。
特に専門用語や業界固有の略称をそのまま使用すると、読者が内容を理解しづらくなる場合があります。
正式名称を用いると文章が読み難くなってしまう場合は、初出時以降を略称で記載すると良いでしょう。
著作権の侵害
他人の画像や文章を無断で使用してしまう「著作権侵害」があります。
特にWEBライティングでは、手軽にインターネット上から情報や素材を取得できる分、この問題に無自覚な場合が多いです。
著作権とは
著作権とは著作物を作成した人が持つ権利で、この権利を守るために著作権法があります。
ネット上に一般公開されている画像や文章だからといって自由に利用できるわけではありません。
それが個人や企業が作成したものである限り、誰かの著作物です。無断使用はNG行動となりますので十分注意しましょう。
著作権を侵害しないようにするには
- コピペをしない
- 転載の許可をもらう
- 引用した際は引用部分を明確にし、引用元を記載する
- 素材サイトを利用する
文章については他人の表現をそのまま使用するのではなく、リサーチをもとに自分の言葉で再構成することが基本です。
写真やイラストについては「素材サイト」がおすすめです。著作権フリーの素材を上手に活用することで、リスクを回避できます。
しかし、場合によっては利用に制限があるため、素材の利用規約をしっかりと読んでからにしましょう。
記事タイトルに誤解を招く表現をしている
タイトルは記事全体の顔とも言える重要な要素であり、読者が記事をクリックするかどうかを左右するポイントです。
内容とズレたタイトルや過剰に煽る表現はユーザーがすぐに記事から離れてしまい、直帰率が高くなってしまいます。
注意しないと、検索エンジンからの評価が下がりSEOにも悪影響が出てしまうでしょう。
内容と一致していないタイトル
記事のタイトルが内容と一致していない場合は、読者にとって大きなストレスになります。
例えば、「【初心者向け】失敗しない!ふわふわハンバーグレシピ」というタイトルでありながら、具体的なレシピや調理方法が含まれていなかったら、読者はがっかりするでしょう。
内容との乖離を防ぐために、タイトルは記事で一番伝えたいことや、記事を1文で要約したものにしましょう。
過剰な表現のタイトル
釣りや煽りといった過激な表現のタイトルも使わないようにしましょう。
例えば、「これだけで絶対成功!」「100%効果がある」などの表現は一時的に注目を集める可能性があるものの、読者は知りたい情報も知れず失望感を与えてしまいます。
そうしてユーザーからの評価も下がり、サイトとしての信用も失うと記事の閲覧数が増えても記事本来の目的は達成出来ないでしょう。
まとめ
WEBライターが注意すべき点として、コピペや盗作などの著作権、リサーチ不足による曖昧な情報の記載、タイトルと内容の乖離などがあります。
これらのNG行動を犯してしまうと、ユーザーやクライアントの信頼を失うだけでなく、SEO対策の観点からも悪影響を及ぼします。
WEBライティングでは、読者に正確で有益な情報を提供し、記事を通じて価値を感じてもらうことが重要です。
上記で紹介した注意点をしっかりと守り、継続的にコンテンツの質を向上させながらライティングスキルを高め、より多くの人に読まれる記事を目指しましょう!